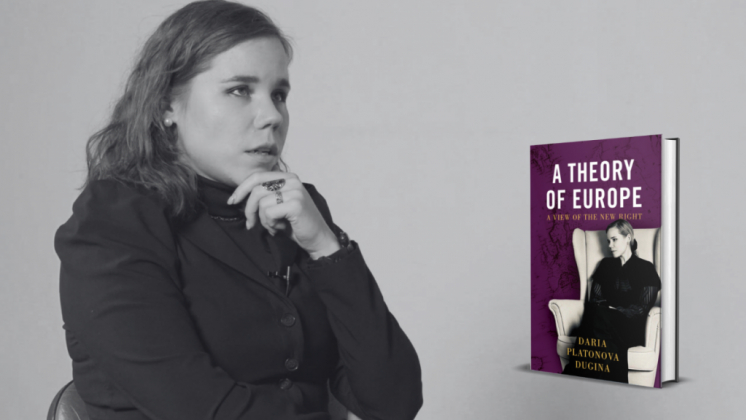「グレイト・ヨーロッパ・スペース」
それが誕生した時、周囲に何が存在していたのでしょうか。そしてフランスでは何が起きていたのでしょうか。疑いなく、当時そこには右派イデオロギーの深刻な危機がありました。当時の右派は、発展を続ける左派リベラルの言説に対して、知的な次元においてすら代案を提示することができず、さらにナショナリズムの殻に過度に閉じこもり、ただひたすらフランスのみを思考の対象としていました。それは、トランプが「アメリカを軸に考える」という姿勢と同質であり、孤立主義的な観点からアメリカを国際関係から切り離すのと同じように、「フランスの主観で考える」という発想でした。
この戦略がアメリカにとってはむしろ良いものであるとしても、ヨーロッパ文化空間の一部であるフランスにとっては、そのような人工的な操作は文化においてより否定的な影響を及ぼし、フランスをヨーロッパとその古典的伝統から人為的に引き離すものとなります。
そのため新右派が最初に行ったことは、彼らに多くの点でインスピレーションを与えたジャン・ティリアールに従い、当時広く受け入れられていたフランス民族主義を拒絶し、代わりにヨーロッパ民族主義を提唱することでした。彼らは「大空間」と「民族の権利」に関するカール・シュミットの地政学的思想に転向しました(1)。
彼らはジャン・ティリアールの大空間の自給自足という構想を発展させました。この理論はもともとドイツの経済学者フリードリヒ・リスト(2)によって定式化され、ドイツと中央ヨーロッパの周辺諸国に適用されたものでしたが、ティリアールはこれを修正してヨーロッパ全体に投影したのです。ベルギー人であったティリアール自身は、小さな空間が独立して生存し、その主権を確保することはできないということをよく理解していました。
戦争を遂行し、アメリカ化・普遍化・グローバリズムに対して物理的にも思想的にも効果的に対抗するためには、ヨーロッパの大空間を形成することが必要です。したがって、ジャン・ティリアールの影響は非常に重要であり、当時の通常の右派とは異なって、新右派は「ヨーロッパを思考する」あるいは「ヨーロッパの観点で考える」ことが必要であると述べました。これが彼らを当時の旧右派と区別し、対立させる要因となったのです。では当時の右派とは誰だったのでしょうか。それは、ピエール・プージャードの追随者である、いわゆるプージャディストたちでした。
ジャン=マリー・ル・ペンとその国民戦線は、後にこの運動から成長することになりました。ル・ペンはプージャディズムとの繋がりを持っており、アクション・フランセーズの創設者であるシャルル・モーラスの精神を継承する王党派と民族主義者たちによる右派運動も存在していました。GRECEは、これらすべてと決定的に断絶したのです。
新右派が後に自分たち自身について記すところによれば、特にアラン・ド・ベノワが1979年にGRECEの11周年にあたって最初の省察を定式化した際に述べたように、「われわれは旧右派との完全な決別を感じました。特に思想の戦線において」ということでした。新右派を分析するための重要な指導書である『Les Idées à l’endroit』において彼が記したように、「旧右派は死んでいた」のです(3)。
旧右派は自らを死に至らしめ、原則的にこれに値する状態でした。したがってGRECEは、彼らが受け入れない右派と、何らかの形で彼らと意見を異にする左派との間の、ある種の断絶の中に自らを見出すことになりました。なぜなら、ド・ベノワが述べたように、左派は経済のトポスの内部に留まり続けており、彼らにとって人間とは何よりもまず経済によって条件づけられる存在だからです。
新右派にとって、人間を条件づけるのは経済ではなく、文化と精神の領域です。したがって左派はGRECEを受け入れません。GRECEが人間生活に対する経済の影響を二次的な位置に置き、むしろ人間の生活が経済的領域によって条件づけられることを否定しているからです。彼らはこれを拒絶するのであり、こうして彼らは実際にある種の亀裂の中に置かれることになったのです。
新右派の初期メンバーの中で最も注目すべき人物として、まずアラン・ド・ベノワを挙げることができ、さらにドミニク・ヴェンナー、そして皆様もお聞きになったことがあるかもしれませんが、ジャン=クロード・ヴァラやピエール・ヴィアルといった人物たちが存在しています。
その他のメンバーについては、それほど著名ではなく、彼らの著作はロシア語にも翻訳されていません。GRECEという名目の下で、新右派は1968年から年次シンポジウムや会議──フランス語で「les colloques」と呼ばれるもの──の組織化を開始しました。
フランス語の「colloque」は「congress」や「symposium」に類するものであり、実際にわれわれの言語でも「kollokvium(コロキウム)」という語を使用しています。これらのコロキウムで取り上げられた典型的なテーマには、「右派からのグラムシ主義」「諸民族の大義」「左派」「右派」「システムの終焉」「世界の終焉」「ヨーロッパ」「新世界」「アメリカ:危険」「ディズニーランドに反対」などがありました。これらのテーマこそが、新右派が自らの知的生活における結節点と見なしている要素なのです。
一つの例として、第15回GRECEコロキウムの講演集『Le cause des peuples』(「諸民族の大義」)があり、ここに主要な講演が収録されています。左派系新聞『ル・モンド』は、新右派が「個性の差異を消去し、すべての人をロボットに変える西欧・アメリカ的システムを標的にした」ことに恐怖を覚えました。このアメリカ覇権とグローバル・リベラリズムへの批判は、一般的にそれらを擁護していた旧右派とは決してかみ合わないものでした。左派にとって同様に衝撃的だったのは、彼らの別のコロキウムで聞かれたグラムシ主義への賛美でした。
1988年には、左派寄りの読者を対象とした特別刊行物『クリシス』を発行し、これは主として左派戦線で活動し、主要なテーマを主に左派的(ただし常に反リベラル的)立場から検討するものでした。このようにして、彼らの出版基盤は『エレメンツ』『ヌーヴェル・エコール』そして『クリシス』となったのです。
歴史と主要人物について概観したところで、次に影響について移りましょう。ここでは、すべてが非常に興味深いものとなります。これらの影響については、おそらく私の講演の大部分を占めることになるでしょう。なぜなら、すでに述べたように、新右派は一種の百科事典的存在であり、彼らが誰から影響を受けたかについて論じることは、本質的に彼らの主要なテーゼと概念に親しむことになるからです。
第一に、新右派はあらゆる戦線において保守革命家たちから強い影響を受けました。これには、エルンスト・ニーキッシュの精神を継ぐ左派的な国家ボルシェヴィキから、オズワルト・シュペングラーやカール・シュミットのような右派的保守革命家、さらにはエルンスト・フォン・ザロモンやハロ・シュルツェ=ボイゼンといった左派的保守革命家まで含まれています。1920年代から40年代にかけてのドイツ非順応主義的文化のこの全層が、フランスの文脈に入り込み、新右派の思考構造に統合されていったのです。
彼らはこの知的環境を普及させ、エルンスト・ユンガーを非常に愛好していました。ド・ベノワ自身はユンガーと実際に面会し、その秘書であったアルミン・モラーと親交を結び、定期的な書簡のやり取りを維持していました。彼はユンガーの「森林の通路」のような思想からインスピレーションを得ており、これは近代文明を離脱し、それに根本的に対抗して、精神が経済を支配する伝統の領域へと回帰することを意味しています(4)。
戦争に関するユンガーの思想もまたアラン・ド・ベノワを魅了し、とりわけクシャトリヤ精神の本質を深く描写した点に強く惹かれていました(5)。この思想的系譜は新右派全体を貫く指導線として流れています。
さらに重要なのは、ダブリンからウラジオストクまでの統一ヨーロッパの理論家であるジャン・ティリアールの影響です(6)。この構想は最初にジャン・ティリアールによって宣言されたものであり、今日ではロシアの政治家を含む多くの人々によって使用されています。ダブリンからウラジオストクまで(あるいは別の表現ではリスボンからウラジオストクまで)の大ヨーロッパを確立するというテーゼは、ジャン・ティリアールの発案でした。彼はヨーロッパ諸国とロシアを含むヨーロッパ大陸の統合、単一のヨーロッパ空間の創設の必要性を説いています。ティリアールの結論によれば、この集団の地政学的アイデンティティはランド、すなわちテルロクラシー(陸権)です。それは反グローバリズムであり反普遍主義であり、アングロサクソンおよび大西洋主義的地政学に対する対立軸となります。この大ヨーロッパの地域、この極は、伝統の再生、平等主義と普遍主義に対するクーデター、失われた伝統の復活のための基盤となるべきものです。
したがって、新右派がヨーロッパという現象を眺め、ヨーロッパ文明の再生の必要性について語るとき、彼らは多くの点でティリアールに従っているのです。彼らがこのヴィジョンの中にロシアをヨーロッパ空間の重要な一部として含めていることもまた、特に重要な事です。
1.Carl Schmitt, Völkerrechtliche Großraumordnung mit Interventionsverbot für raumfremde Mächte. Ein Beitrag zum Reichsbegriff im Völkerrecht (Berlin: Duncker & Humblot, 1991)
2. Friedrich List, The National System of Political Economy, trans. Sampson S. Lloyd (London: Longmans, Green and Co., 1909).
3. Benoist, Les Idées à l’endroit, 57.
4. Ernst Jünger, The Forest Passage, trans. Thomas Friese (Candor: Telos Press Publishing, 2013).
5. Ernst Jünger, Storm of Steel, trans. Michael Hofmann (New York: Penguin Books, 2016). The Kshatriya is a member of the warrior and ruler caste in traditional Hindu society, responsible for protecting and governing, embodying values of courage, strength, and honour.
6. Yannick Sauveur, Jean Thiriart et le national Communautarisme européen. mémoire présenté devant l’Institut d’études politiques de l’Université de Paris (Charleroi: Editions Machiavel, 1983).
翻訳:林田一博